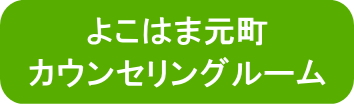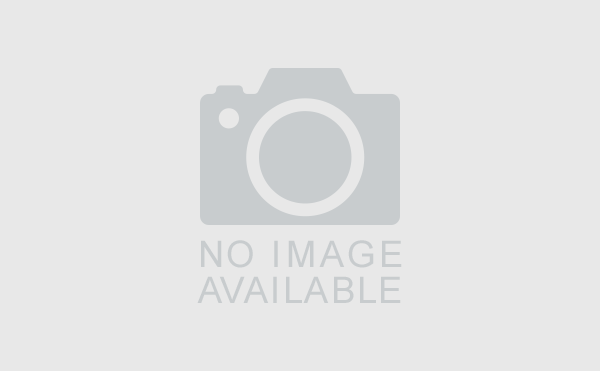【カウンセリングの方法論について①~「カウンセリング」と「心理療法」の違い】
当ブログで、これからカウンセリングあるいは心理療法の方法論について簡単に解説していくつもりですが、その前に「カウンセリング」と「心理療法」という用語の違いについて触れておきたいと思います。まず、手元にある有斐閣現代心理学辞典を見てみると、
*カウンセリング…「言語的及び非言語的コミュニケーションを通して、相手の行動の変容を援助する人間関係」であって、「カウンセラーに限らず、広く対人援助の専門職がかかわる業務の一側面」
*心理療法…「精神療法」と同義であり、「クライエントや患者の問題解決や症状の解消法のための心理的援助法を、専門の訓練を受けた心理臨床家や医師(精神科医や心療内科医)が行う治療あるいは援助行為」
と定義されています。
ネット上でいろいろなサイトを見てみると、やはりクライエントの語りに耳を傾け、共感的に理解をして成長を促すのが「カウンセリング」で、例えば認知行動療法や家族療法のような、特定の技法によって気持ちや行動の変容を促すのが「心理療法」という区別が多いようです。「カウンセリング」よりも「心理療法」の方が、より専門的な方法であるという印象を受けます。
ただ、一般の方にはこの区別はわかりにくいのでは…と思い、さらにネットを見ていると、「カウンセリングルームセンター南」様のサイトで興味深い説明を見つけました。(ちなみに、「カウンセリングルームセンター南」様には、以前の仕事のときから大変お世話になっております。)そちらによると、「セラピー(心理療法とほぼ同義)」とは、医学用語の『治療』にあたる言葉であり、「カウンセリング」とは、アセスメント、見立てて、セラピーを行う一連の流れ全てのことで、医学用語の『診療』にあたる言葉である、としています。「カウンセリング」を心理的支援における全体の流れとしてとらえているようで、この説明は、個人的にはとても腑に落ちます。興味のある方は、下記をご参照ください。
https://crcm.jp/counseling-therapy
なお、今後のブログでは、必ずしもこの説明に沿わず、引用・参照した文章に沿って使用している場合もありますので、その点はあらかじめご承知おきください。また、同じように「クライエント」と「相談者」という用語については、一般的に使用されるカウンセリングの対象者については「クライエント」を使い、当ルームでの対象者という意味では「相談者」を使用していきます。