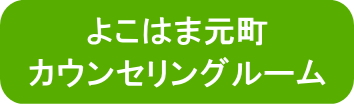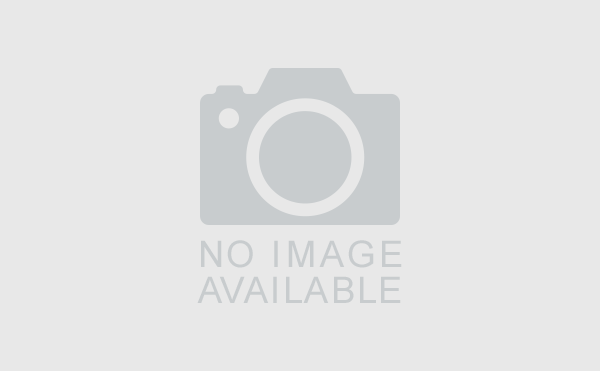【カウンセリングの方法論について③~認知行動療法について】
認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy;CBTと略すことがあります)の起源は、バンデューラの社会的学習理論とするものや、ベックの認知療法とするものなど、諸説あるようですが、いずれにしてもアメリカで生まれ、発展した心理療法の一つで、現在は治療効果があると認められる(すなわち、エビデンスに基づいた)もっとも有力な療法と、一般的には認識されています。ただし、理論的枠組みと実施方法には多くのバリエーションがあり、簡単に説明することは難しいのですが、共通する特徴としては、問題となる行動に影響を及ぼすクライエントの認知(ものの見方や考え方)に焦点を当て、パターン化して問題の解決に結びつかない認知を修正していくことで、問題行動を変えていく、と言えるかと思います。(日本認知療法・認知行動療法学会のwebサイトを参考にさせていただきました)
このときの認知の扱い方や修正の方法等で、いろいろな違いがあるようで、多くのカウンセラーは主となる方法を定め、実際の臨床場面で、それぞれ工夫をしているようです。私は、大学院のときの指導教官が認知行動療法の先生であったので、概要を学び、その後の研修等で「自動思考」「スキーマ」を修正するオーソドックスなやり方を勉強してきました。
ただ、その後は次第に、後日ブログで取り上げる予定の短期療法(Brief Therapy)、とくに解決志向アプローチ(Solution Focused Approach)や家族療法におけるシステムズアプローチの有用性に気持ちが傾き、そちらをメインとすることが多くなっています。もちろん、ご相談者様の状態やご希望に合わせて、認知行動療法も活用していきます。