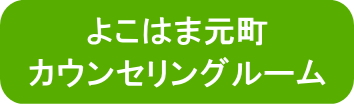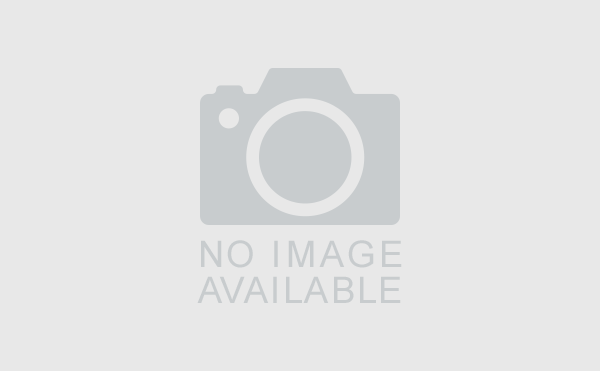【カウンセリングの方法論について④~家族療法について】
私も所属している一般社団法人日本家族療法学会のwebサイトによると、「家族療法(Family Therapy)は、1950年代から欧米を中心に発展してきた精神療法・心理療法であり、家族という文脈からクライエントや家族への理解と支援を行う対人援助の大きな領域」であると記されています。
具体的な進め方には、実に多くの理論や技法があり、このスペースでは紹介できません(私も語るほどの知識はないのが正直なところです)が、クライエントが直面している問題を「原因→結果」という因果論ではなく、家族も含めた人間関係や社会における関係性(とくにコミュニケーション)によって維持されていると考え、介入するアプローチ、とまとめてみることができます。
理論的なことは他の専門書にお任せしますが、実際に私が実感したこととして、家族療法では
・個人に原因を求めず、悪者探しをしないため、クライエントに抵抗感が少ない。
・人間関係や社会への介入にはいくつかのアプローチが可能(正解は一つではない)であるため、クライエントが取り組みやすいところから始められる。
・少しでも変化の兆しが起これば、それを広げていくことで短期間で終結する場合も少なくない。
など、クライエントにとって負担の少ない方法の一つと言えます。
一方で、カウンセラーが介入のポイントを見誤ったり、変化が起きにくい場合など、カウンセラー側の対応に不備があると、なかなかスムーズに行かない場合もあります。
なお、家族療法という名称から、家族(とくに複数の家族成員)を対象にカウンセリングを行うイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、問題に直面している方でもそのご家族でも、お一人にお越しいただいてカウンセリングを進めていくことも可能ですし、それができることが家族療法の強みだと言えます。