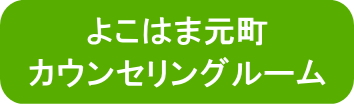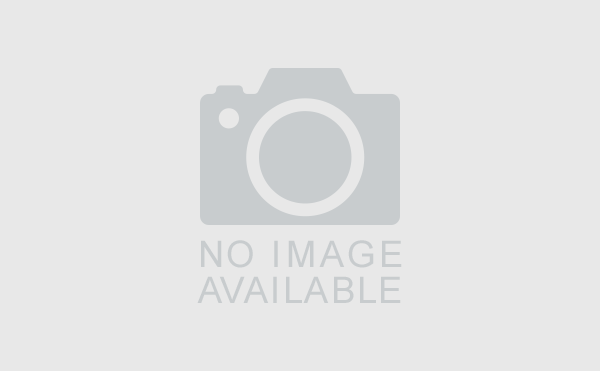【カウンセリングの方法論を超えて~クライエントとの関係性について】
これまで、カウンセリングの方法論について述べてきました。カウンセラーにとって、核となるカウンセリングの方法(スキル)を身につけることは必須であり、軸となるものです。ただ、カウンセリングを実践している方の多くが、自分にとって中心となる方法をベースに、臨床現場では様々な工夫を凝らしているようです。また、いろいろな文献を読み、様々なカウンセリングの方法論について学んでいると、そこにいくつかの共通点を見出すことがあります。
では、カウンセリングにおいては何が重要なのでしょうか。少し古い文献になりますが、『心理療法・その基礎なるもの』(スコット・D・ミラー他著,金剛出版,2000)という本で、著者らは多くの文献を総括して心理療法における有効要因を分析しています。そのなかでもっとも有効な要因が「クライエント要因」と「治療関係要因」であるとしています。ここでいう「クライエント要因」というのは、治療の成否がクライエント次第という意味ではなく、カウンセラーがクライエントのもつ力や可能性をどれだけ発揮させられるか、という意味だと思います。福祉の世界でよく言われる「エンパワメント」に近いものではないでしょうか。「クライエント要因」を有効に機能させるためにも、クライエントとカウンセラーとの良好な「治療関係」を結ぶことが重要だといえると思います。(本の内容に関する個人的な解釈に基づくものですので、多少の解釈の違いはご容赦ください…)
もう少しかみ砕いた表現をすると、カウンセラーがクライエントの訴えを真摯に聴き、問題となっていることについてのクライエントの理解と対処をカウンセリングの場で共有し、少しずつでも解決に向かうよう、クライエントとの信頼関係を構築していくこと、と言えるかもしれません。その際にカウンセラーは自らの持つ専門的なスキル(方法)を利用するわけですが、先ほどのミラーらの分析によれば、その方法の違いはさほど重要な要因ではないとのことです。
もちろん、専門的なスキルを持ち、それを利用できることはカウンセラーに必須のことであり、そのために専門的な資格が求められています。専門的なスキルや知識を持たず、熱意だけでクライエントに関わることは厳に慎むべきですが、カウンセリングにおけるもっとも基本的なこととして、クライエントに真摯に向き合う姿勢と意識が大切だと言えるのではないでしょうか。